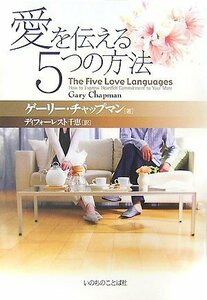人間関係
- 初ナイトクルーズ!ゆめのたね放送局10周年記念パーティに参加しました
- スカイツリーとともだち
- 「女性のスキルアップ」って、なんですか? 〜家事も育児も、スキルアップが必要なのは誰なのか〜
- 不機嫌をまき散らす迷惑な人になってませんか?
- きっとだいじょうぶ スキーキャンプに参加しています
- 男性が「助けを求める」のが苦手な理由~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ④
- 本当の強さとは? 男性のレジリエンスについて考える
- 家庭と趣味を両立するために、まずやるべき3つのこと~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ②
- 子育て夫婦のすれ違いを解消する ほんのおすすめ
- 夫が自ら気づき変わると、もっと幸せになれる~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ①
-
初ナイトクルーズ!ゆめのたね放送局10周年記念パーティに参加しました

いつもご覧いただきありがとうございます!
昨日はゆめのたね放送局10周年記念パーティがありました。これまでも、毎年周年パーティはあったんですが、子どもが小さかったり、資金的に優先することが他にあったりで、沖縄や横浜での開催には参加できずにおりました。今年は私も放送開始からまる4年経ち、徐々にパーソナリティの知人・友人も増えてきたし、且つ局が10周年という節目。しかも、会場が、関西人なら染みついているCM「ルミナ~ス神戸 ツーーー(エコー)」神戸港の中ふ頭を出発して、明石海峡大橋をくぐって戻るクルーズです。アレに乗れるチャンスはそうそうないで!ということで、子どもも連れていくことを決めていました。ただし、時期が中学の中間テストや運動会と重なる、ということで、「2年からは登校するかもしれない」と言っていた長男は申し込みせず。結果的には登校していないから、物理的には行けたんですけど、思春期の息子たちは兄弟仲が最悪で、もうずっと冷戦状態。
一緒にクルマで移動するのはムリなので、次男だけ同伴しました。小学校をサボれて、美味しいものがいっぱい食べれて、と、次男はとても楽しみにしてくれていました。10時過ぎに自宅を出発して、途中昼食を摂って、14時くらいに神戸港に到着。途中、43号線を通ったので、「阪神淡路大震災の時に倒れたのがこの上の高速なんやで」というと、「えぇぇ!」そもそも次男はあの震災が起きた場所を大阪やと認識してたらしくて、その地に赴いて歴史を伝えるのは大切なことやなと感じました。実は次男2歳の誕生日記念で、アンパンマンミュージアムには来ているのです。本人は全く覚えてませんでしたが(笑)。程よい天候のもと、海辺を散策。 メリケンパーク側から、この後乗り込むルミナス神戸Ⅱを眺めてみる。
メリケンパーク側から、この後乗り込むルミナス神戸Ⅱを眺めてみる。 乗船してからの眺め①
乗船してからの眺め①
川崎重工のドックがあった。 乗船してからの眺め②
乗船してからの眺め②
反対側には、長らく購入を続けたフェリシモの本社ビルを発見。しばらく前に、近くにある名所 ポートタワーの管理業務を受注したとかで、中の活用も昔とまるっと変わって、すっかりフェリシモチックになったようですよ。さて、最悪シミュレーションを自動でできてしまう、災害に敏感な私。救命胴衣の位置・数量と、取り出しやすさをチェック。大人用と子ども用がわかりやすく収納されていました。あちこちにこのBOXが設置してあって、さすがの危機管理だなと思いました。義務ですけどね。乗船の数週前には、名簿の提出も求められました。海難事故の際に備えてですね。すぐに自分の意志では逃げられない乗り物に乗る緊張感があります。 救命ボートの撮影を忘れましたが、見た限りでは、55人乗りのボートが10個くらい小さくパックされていました。これらも複数個所に分散して設置してあり、船内のどこでトラブルがあっても、脱出ができるような仕組みでした。
救命ボートの撮影を忘れましたが、見た限りでは、55人乗りのボートが10個くらい小さくパックされていました。これらも複数個所に分散して設置してあり、船内のどこでトラブルがあっても、脱出ができるような仕組みでした。 うちの小学生男子がとにかく探検に誘うので、自分だけなら絶対行かなかったところにも入り込んで、出航前だったからか、ドア開けっ放しの操舵室を覗いてドキドキ。「こういう仕事もカッコイイね!」とか言いながら、面舵と取舵、どっちが右でどっちが左か?っていう認識を新たにしていました。出航の準備作業をデッキから観察して、その仕組みに大興奮もしていましたよ(笑)。パーティのドレスコードは、基本的なスーツやドレスなんですが、それぞれが番組パーソナリティですので、番組のコンセプトに合っていればOK!となっていました。従いまして、私の服装ははい!ドーン!
うちの小学生男子がとにかく探検に誘うので、自分だけなら絶対行かなかったところにも入り込んで、出航前だったからか、ドア開けっ放しの操舵室を覗いてドキドキ。「こういう仕事もカッコイイね!」とか言いながら、面舵と取舵、どっちが右でどっちが左か?っていう認識を新たにしていました。出航の準備作業をデッキから観察して、その仕組みに大興奮もしていましたよ(笑)。パーティのドレスコードは、基本的なスーツやドレスなんですが、それぞれが番組パーソナリティですので、番組のコンセプトに合っていればOK!となっていました。従いまして、私の服装ははい!ドーン! アロンソさまのアストンマーチンチームウェアとキャップ!こんな人、他に誰もいなかったので、インパクトは与えたはず(笑)お話ししているのは、多くの後進を指導されているスタジアムDJ・FMラジオDJの玉井智さん。パーソナリティの育成でゆめのたねに関わっておられます。私も番組内容・構成などで悩んだときに、相談に乗っていただきました。その後どうなったか?ご報告をしておりましたよー。モータースポーツに振り切って、楽しく続けられるようになったことを、一緒に喜んでくださいました。他にも、コンサルタントの幸田涼さんは、全然違った視点で気づきを与えてくださる不思議な方。社会貢献を意識するあまり、楽しく続けることができなくなっていた時に、相談に乗っていただきました。ライフオーガナイズの魅力や可能性についても、よく理解してくださっているので、近況をお伝えすると、とても喜んでくださいました。次男はお料理を食べて食べてジュース飲んでまた食べて、出し物を楽しんで、デッキに出たり戻ったり。バルーンアートのお姉さんにゴマちゃんをつくってもらったり、テーブルマジックの横をまじまじ見ながら通り過ぎたり、DJブースや騒いでいる変わった大人たちの様子を眺めたり。歌やハワイアンダンスなどの出し物もあり、全部見るのは難しかったです。そんな中でも、「ステージマジックは絶対見る!」と時間を気にしていた彼。マジシャンはMr.マリックの弟弟子?かなにか(聴き逃した)のMr.オクチ氏。ステッキマジック輪っかのマジック2種(少年や元少年少女が多数お手伝い)ハンカチのマジックトランプのマジック(次男がお手伝い)テーブル浮遊マジック始まるまでは、「仕掛けを見破る!」と意気込んでいた彼でしたが、結局さっぱりわからず(笑)。目をキラキラさせて、いろいろな「初めて」を全身で楽しんでいて、何度も何度も「今日のことは絶対に忘れない!」って言ってました。そんな彼の様子を見ていて、子どもは二人!離婚するにしても二人産んでから!と覚悟して、本当に離婚を決めて彼が4か月の時に別居することになって、それからいろいろと申し訳ないなと思ってきたけれど、私の人生に彼がいてくれてほんとによかった、と思いました。長男と二人で生きていく人生だと、何かと長男に関わりすぎる、とか、依存してしまう未来が見えていました。そこに次男がいることで、うちの家族はおもしろく絶妙なバランスを保っていると思っています。明るくおバカに振舞う次男は、自称陰キャの長男とは対照的なキャラクターで、私の子育ての視点を広げてくれてラクにしてくれています。私が人の親をやることになって、毒親になっちゃう気しかしなかったのを、踏みとどまらせてくれている存在です。不安しかなかったけど、この子たちと一緒に生きてきてよかったなと感じた一日になりました。それから!
アロンソさまのアストンマーチンチームウェアとキャップ!こんな人、他に誰もいなかったので、インパクトは与えたはず(笑)お話ししているのは、多くの後進を指導されているスタジアムDJ・FMラジオDJの玉井智さん。パーソナリティの育成でゆめのたねに関わっておられます。私も番組内容・構成などで悩んだときに、相談に乗っていただきました。その後どうなったか?ご報告をしておりましたよー。モータースポーツに振り切って、楽しく続けられるようになったことを、一緒に喜んでくださいました。他にも、コンサルタントの幸田涼さんは、全然違った視点で気づきを与えてくださる不思議な方。社会貢献を意識するあまり、楽しく続けることができなくなっていた時に、相談に乗っていただきました。ライフオーガナイズの魅力や可能性についても、よく理解してくださっているので、近況をお伝えすると、とても喜んでくださいました。次男はお料理を食べて食べてジュース飲んでまた食べて、出し物を楽しんで、デッキに出たり戻ったり。バルーンアートのお姉さんにゴマちゃんをつくってもらったり、テーブルマジックの横をまじまじ見ながら通り過ぎたり、DJブースや騒いでいる変わった大人たちの様子を眺めたり。歌やハワイアンダンスなどの出し物もあり、全部見るのは難しかったです。そんな中でも、「ステージマジックは絶対見る!」と時間を気にしていた彼。マジシャンはMr.マリックの弟弟子?かなにか(聴き逃した)のMr.オクチ氏。ステッキマジック輪っかのマジック2種(少年や元少年少女が多数お手伝い)ハンカチのマジックトランプのマジック(次男がお手伝い)テーブル浮遊マジック始まるまでは、「仕掛けを見破る!」と意気込んでいた彼でしたが、結局さっぱりわからず(笑)。目をキラキラさせて、いろいろな「初めて」を全身で楽しんでいて、何度も何度も「今日のことは絶対に忘れない!」って言ってました。そんな彼の様子を見ていて、子どもは二人!離婚するにしても二人産んでから!と覚悟して、本当に離婚を決めて彼が4か月の時に別居することになって、それからいろいろと申し訳ないなと思ってきたけれど、私の人生に彼がいてくれてほんとによかった、と思いました。長男と二人で生きていく人生だと、何かと長男に関わりすぎる、とか、依存してしまう未来が見えていました。そこに次男がいることで、うちの家族はおもしろく絶妙なバランスを保っていると思っています。明るくおバカに振舞う次男は、自称陰キャの長男とは対照的なキャラクターで、私の子育ての視点を広げてくれてラクにしてくれています。私が人の親をやることになって、毒親になっちゃう気しかしなかったのを、踏みとどまらせてくれている存在です。不安しかなかったけど、この子たちと一緒に生きてきてよかったなと感じた一日になりました。それから! 下船後ですが、ゆめのたねでも防災の活動をしているので、オンラインミーティングでしか見たことのない人たちと対面して話し、名刺交換などもして記念撮影。全国に散らばっているので、こういう時でもなければなかなか会えませんね。
下船後ですが、ゆめのたねでも防災の活動をしているので、オンラインミーティングでしか見たことのない人たちと対面して話し、名刺交換などもして記念撮影。全国に散らばっているので、こういう時でもなければなかなか会えませんね。
 着いてすぐ、昼間のポートタワーと、解散後の夜のタワー。美しいものが大好きな次男は、こういう景色も楽しんでいました。
着いてすぐ、昼間のポートタワーと、解散後の夜のタワー。美しいものが大好きな次男は、こういう景色も楽しんでいました。義理・宣伝・娯楽が1/3ずつかな?という、初のナイトクルーズパーティでした。
個人で乗船すると、たぶんもっとお高いだろうルミナス神戸Ⅱですから、よい機会・経験になりました。スタッフとして大活躍してくださってた、事務局のみなさんと各スタジオのリーダーさんお仕事中だからなかなか話しかけづらかったけど、サイトでだけ見ていたあの人や、オンラインサロンでご一緒したことのある!というあの方も、リアルで見れてよかったです。ありがとうございました。防災部活動もがんばっていきたいです。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
あきよさんに会いたかったのに見つけれんかったなぁ。
また今度ぜひ!ラジオ、聴いてくださいね!
6月のゲストは、激務サラリーマンと夫と父をやりつつモータースポーツ系の発信を精力的に行っている、レーサーでYouTuberのもみちゃんです。過去放送分も配信しています。 -
スカイツリーとともだち

いつもご覧いただきありがとうございます!
先日の上京話の続きです。初体験!小劇場観劇 いつもご覧いただきありがとうございます!先月のことになりますが、ひっさしぶりに上京しまして、観劇してまいりました。こちらの劇場で、初めて、友人の俳優としての雄姿を見る、という目的でした。演目は【CRIMES OF THE HEART】19...時系列としては、正確には観劇の前の話です。始発で最寄り駅を出発して、8時過ぎにひっさしぶりの東京駅に。だいたい品川駅だったんですよね。変わったような変わってないような。相変わらず訳の分からないこと言ってます っていう歌が脳内に流れるくらい人が多いです。自宅付近よりもギュッとしてる印象の東京ですが、ここからスカイツリーのある押上までは小一時間かかりました(笑)。遠くから見てるより広かったんですね。いつも行くところが限られていたので、よくわかってなかったです。10時から展望台営業開始のため、早めに到着しようとしておりまして、始発移動だったんです。この日はあかねちんこと平沢あかねさんを誘っておりました。彼女の夫は転勤族。以前は名古屋にも住んでました。私が初めて出会ったライフオーガナイザー3人のうちの一人で、「めちゃ感じの良い素敵な人やん」「こんな人になりたいなー!」と思ったんです。それ以来、彼女がどこに転居しても、変わらず励ましあって、いろいろ乗り越えてきました。ラジオにも出てもらいました。そんなあかねちんと、カフェで待ち合わせて、ひとしゃべりしてから展望台の列に。 あいにくの曇り空。せっかく展望台に上りましたが、東京タワーですら見えなかったです。
あいにくの曇り空。せっかく展望台に上りましたが、東京タワーですら見えなかったです。 4基あるエレベーター内はそれぞれ東京の四季を表現する装飾があるそうで、これは夏の花火ですね。江戸切子なのかな?とてもきれいでした。
4基あるエレベーター内はそれぞれ東京の四季を表現する装飾があるそうで、これは夏の花火ですね。江戸切子なのかな?とてもきれいでした。コナンの映画公開と時期が重なってたのもあり、ツリーの中はパネルとかがいっぱい。
推し活の若い子たちがたくさん来てました。 ガラスの床部分。他の誘導路は適切でわかりやすく迷うこともなかったのに、ここだけ動線が混乱していて、修学旅行生がうじゃうじゃ滞留。ライフオーガナイザー的には「やり直し!」と言いたくなるマズさでしたが、どうなんでしょうね?
ガラスの床部分。他の誘導路は適切でわかりやすく迷うこともなかったのに、ここだけ動線が混乱していて、修学旅行生がうじゃうじゃ滞留。ライフオーガナイザー的には「やり直し!」と言いたくなるマズさでしたが、どうなんでしょうね? ひと通り見て、早めのランチ。何を食べようか?悩む様子もカワイイあかねちん。体調のこととか、仕事のこと、ちょうどチャリティの準備中だったのでその話とか、いろいろ話して、あっという間に各々次の予定に向かう時間に。ひとりでスカイツリーも行けたけど、付き合ってくれてうれしかったです。そして観劇の後…。よくわからず新宿に行きたいただそれだけで、劇場最寄りの西武沿線から新宿に向かってしまい、バスタ付近までめっちゃ歩くことになってしまったんです(笑)。途中で乗り換えたらよかったんやな。なんやねん東京。遠いがな!スタスタ歩いて、こちらは急遽誘ったかおりんこと塚本香央里さんと合流。かおりんとは、メンタルオーガナイザーの資格認定講座で一緒になり、その後何かがきっかけで距離が縮まったんですよね。私もクラシックを齧ったことがあるので、プロのバイオリニストである彼女の影の苦労がめっちゃわかる。
ひと通り見て、早めのランチ。何を食べようか?悩む様子もカワイイあかねちん。体調のこととか、仕事のこと、ちょうどチャリティの準備中だったのでその話とか、いろいろ話して、あっという間に各々次の予定に向かう時間に。ひとりでスカイツリーも行けたけど、付き合ってくれてうれしかったです。そして観劇の後…。よくわからず新宿に行きたいただそれだけで、劇場最寄りの西武沿線から新宿に向かってしまい、バスタ付近までめっちゃ歩くことになってしまったんです(笑)。途中で乗り換えたらよかったんやな。なんやねん東京。遠いがな!スタスタ歩いて、こちらは急遽誘ったかおりんこと塚本香央里さんと合流。かおりんとは、メンタルオーガナイザーの資格認定講座で一緒になり、その後何かがきっかけで距離が縮まったんですよね。私もクラシックを齧ったことがあるので、プロのバイオリニストである彼女の影の苦労がめっちゃわかる。
会うなり近くのベンチでいろいろと話し込み、寒くなったなぁとごはんに。ここでもいろいろと話しました。ご飯もおいしくて楽しかったー! この日はふたりともに、「ヒラリーは全然気ぃ遣わんで安心しておれるー」とか
この日はふたりともに、「ヒラリーは全然気ぃ遣わんで安心しておれるー」とか「ヒラリー好きよ」など言ってもらって、私の友情が一方通行じゃないことを確認出来て幸せでした。
この後は24時発の夜行バスに乗るまでひたすら人間観察をして過ごし、翌朝6時半過ぎに白子駅に到着!ほとんど寝れませんでしたが7時過ぎの始発路線バスで帰宅して、お昼前にはサーキットでSuper耐久を観てました!なぜ新幹線で当日に帰宅しなかったのか?それは最繁忙期に突入した新幹線に乗るのがイヤだったから。それにしてもこの週は、なぜか大事な用事が集中してしまい、本当に謎ストラテジーでしたが、全部楽しめてよかったです。今日は日記的になりましたが、記録として置いておきます。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
「女性のスキルアップ」って、なんですか? 〜家事も育児も、スキルアップが必要なのは誰なのか〜
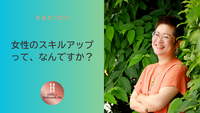
いつもご覧いただきありがとうございます!
本日は、ちょっと一言モノ申すブログとなります。
ここ数日、「女性のスキルアップが必要だ」という発言を、とある政治家がした、という報道がありました。
以前から度々、立場ある男性がこういった発言を繰り返しているのですが、
そういうものを聞くたびに私は、「これ以上何をさせたいの?」と、心の中でつぶやいてしまいます。もちろん、個々の女性として「学び続けたい」、「成長したい」という気持ちは、私自身も大切にしていることです。
キャリアアップしたいだとか、もっと長時間働きたいだとか、もっと効率よく稼ぎたいだとか、願うことは様々だと思います。スキルアップが無意味だとか、不要だと言いたいわけではありません。
ですが、「女性の」と強調されることで、ここに大きな違和感が生まれます。
しかも、「育休中のスキルアップ」について語られるたびに、「はぁ?」となります。
なんでいっつも「女性」やねん?
なぜ、いつも「女性」ががんばる前提になっているのでしょうか。
社会のため、家族のため、職場のため――、気づけば、女性はいつも男性以上に「何役も」担わされているのが現実です。
家では、家事、育児、介護。
外では働きながら、PTAや自治会などの地域活動にも参加しているにも関わらず、そのうえ自己研鑽としてスキルアップまで求められるとは?
元来多くの役割を当然のようにこなしているのに、なぜさらに「女性の努力」が求められるのでしょうか。
そもそも育休とは、放っておいたらすぐに死んでしまう新生児・乳幼児の命を、24時間休みなく見守らなければならないがために必要な休暇であって、「家にいるから合間に勉強できるよね?」と言ってしまう男性の【わかってなさ】にほとほとうんざりしているんです。だから、私は
「仕事 し か していない男性こそ、家事や育児のスキルアップをするべきでは?」と思います。
女性ばかりに努力を求める構造に疑問を持ってほしい
「女性の社会進出が進んでいる」とよく言われますが、実態はどうでしょうか。
女性が社会で活躍するには、「家庭のことはきちんとやってから」という前提がいまだに根強く残っています。
一方、男性はというと、家事ができなくても、育児に関わらなくても、「仕事ができればOK」と評価されることが多いのではないでしょうか。
しかも、職場の評価では「仕事しかしない男性」と比べて「家事も子育てもしている女性」だと、「仕事しかしない男性」の方が評価される制度が一般的です。
「は?」ですよね。仕事にフルコミットできる方が有利に決まっています。こういった矛盾が、多くの女性を苦しめているのです。
妊娠・出産のたび、社会構造で女性のキャリアが分断される状態を放置しておきながら、もっとがんばれとは何ごとか?女性だけがスキルアップすべき、という前提そのものが、すでにおかしいと思うのです。
家事や育児は、「誰かの役割」ではなく、すべての人のライフスキル
私は、ライフオーガナイザーとして、「思考の整理から始める片づけ」を提唱しています。
けれど今こそ、日本社会全体が「思考の整理」を必要としているように感じています。
家事をする=女性だから当たり前、
育児に関わる男性=やらなくていいことをやって偉い、
といった、時代遅れな価値観は、もう手放すべきです。
家庭を維持するために必要な家事や育児は、性別にかかわらず、すべての人にとって必要な「ライフスキル」なのです。
それを「女性がやるべきこと」として押しつける構造が、今なお根強く残っている現実。
自分のこともできないオジサン・オジイサンだけでなく、そんなオジサンたちを増長させてきた《女性であるオバサン・オバアサン》までもが時代錯誤な「こうあるべき」を押し付けて来るんだから、今の子育て世代はたまったものではありません。この構造を見直さずに、「女性のスキルアップ」ばかり叫ばれても、的外れ感しかありません。
そもそもは、家事も育児もできない「男こそ、一人前の大人になれるようにスキルアップするべきなんだぜ?」と思います。社会を変えるには、まず「声を上げること」から
こうしてブログに書くことも、私なりの「声を上げる」手段のひとつです。
同じようにモヤモヤしているけど、うまく言葉にできないという方の、代弁ができたらと思っています。
今こそ、「なぜ女性ばかりが何重もの多大なる責任を負わされるのか?」という問いを、遠慮せずに投げかける時ではないでしょうか。
「男性も変わるべき」「社会の仕組みそのものを見直すべき」という声が、もっと大きく、もっと当たり前に語られるようになってほしいと思います。
女性のスキルアップが「社会構造を変えずに、女性だけに努力を押しつけるための方便」になっているなら、それは違うと言いたいのです。
本当に必要なのは、「女性のスキルアップ」ではなく、「男性の意識改革」、
そして社会全体の構造のアップデートではないでしょうか。すべての人が、当たり前に暮らしを担い、生活と向き合い、自分の人生を整える。
そんな社会に、一歩ずつ近づけていきたいと、私は心から願っています。めっちゃ熱く語りましたが、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
「そうだそうだ!」とご賛同いただけましたら、ぜひシェアしていただけますとうれしいです。そして選挙の際はぜひ投票に行きましょう。
議会で寝てばかりの高齢男性が好き勝手する現状を変えましょう!では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
不機嫌をまき散らす迷惑な人になってませんか?
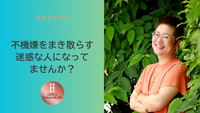
いつもご覧いただきありがとうございます!
今日は、まじめに考えてみた系でございます。
堅い内容と表現となっております。[#機能置換タグ_TOCCLOSE:目次(クリックすると開きます)#]夫が自分の機嫌を取れない家庭の悪循環と、その解決策
家庭内で夫が不機嫌をまき散らすことに悩んでいる女性は少なくありません。
会社では一定の態度を保てるのに、家では不機嫌を隠そうとしない。
これは一体何どういうことなんでしょうか?夫の不機嫌が家庭に及ぼす影響は大きく、妻や子どもにとって深刻なストレスの原因となります。
特に、「自分の機嫌を自分で取る」という習慣がない夫の場合、その影響は家庭だけでなく、夫自身の幸福度や社会的な関係にも悪影響を及ぼします。
ここでは、夫が不機嫌をまき散らすことによる問題点、なぜ妻をはじめとする家族に対してそのような態度を取るのか、そしてその解決策について考えてみます。
夫の不機嫌が家庭に及ぼす悪影響
家庭の雰囲気が悪化する
夫の機嫌が悪いと、家全体がピリピリした雰囲気になります。
家族全員が夫の顔色をうかがうようになり、自由に意見を言ったり、リラックスした時間を過ごしたりすることが難しくなります。
妻の精神的負担が増える
夫が自分の機嫌を取れず、不機嫌をぶつけると、妻はその対応に追われます。
機嫌を取ろうと気を遣ったり、余計な争いを避けるために我慢したりすることで、妻自身のストレスが増大します。
子どもに悪影響を与える
家庭の空気が重くなることで、子どもも萎縮しがちになります。
安心して自己表現ができない環境では、子どもの自己肯定感が低くなり、親子関係や将来の人間関係にも悪影響を及ぼします。
また、子ども自身が「怒りで感情を表現する」ことを学んでしまう可能性もあります。
夫婦関係の悪化につながる
不機嫌をまき散らされる側は、次第に耐えきれなくなります。
夫が何も考えずにイライラをぶつけているうちに、妻の気持ちが冷め、夫婦間の溝が深まってしまうことも少なくありません。
なぜ夫は家庭でだけ不機嫌をまき散らすのか?
多くの夫は、会社では感情をコントロールできているのに、家ではそれができません。
これは、家庭では「甘え」が許されると思っているからです。
社会人として職場での振る舞いを意識している間は、相手に敬意を払うことができるのに、家に帰るとその意識がなくなり、気を抜いてしまうのです。
この背景には、妻に対する無意識の「軽視」や「甘え」があるのかもしれません。
「家族だから、何をしても許される」「気を遣う必要がない」と思っていると、知らず知らずのうちに妻を都合の良い存在として扱ってしまうのです。
しかし、これは大きな間違いです。
家族こそ、最も大切にするべき人間関係であり、最も配慮を必要とする関係です。
夫が自分の機嫌を取れるようになるとどうなるか?
家庭が穏やかになる
夫が自分の感情をコントロールできるようになると、家庭の空気が一気に変わります。
妻も子どもも安心して過ごせる空間が生まれ、夫自身もリラックスできる場所を持てるようになります。
妻のストレスが減る
夫の不機嫌に振り回されることがなくなれば、妻は精神的に安定し、より健やかな関係を築くことができます。
夫婦関係の改善にもつながります。
子どもの情緒が安定する
家の中で安心して過ごせる環境ができれば、子どもは健全に成長できます。
親の顔色をうかがうことなく、自分の感情を素直に表現し、自己肯定感を高めることができます。
夫自身の幸福度も上がる
「自分の感情を他人にぶつけるのではなく、自分でコントロールできる」ということを学べば、夫自身のストレスも減ります。
結果的に、仕事や友人関係、社会生活にも良い影響が生まれます。
夫が自分の機嫌を取るためにできること
自分の感情を自覚する
「なぜ自分はイライラしているのか?」を言語化することが大切です。
日記をつけたり、気持ちをノートに書いたりするだけでも、自分の感情に気づきやすくなります。
ストレス解消の習慣を作る
運動をしたり、趣味の時間を持ったりすることで、ストレスを上手に発散することができます。
「自分の機嫌は自分で取る」と決める
他人に自分の感情の責任を押し付けるのではなく、自分の気持ちは自分で管理するという意識を持つことが重要です。
パートナーを尊重する
家族こそ大切にし、敬意を払うべき存在です。
妻を「甘えられる相手」ではなく、「共に人生を歩むパートナー」として尊重することで、自然と態度も変わります。
家庭は、誰もが安心して過ごせる場所であるべきです。
夫婦がともに成長し、よりよい関係を築いていくためにも、「自分の機嫌は自分で取る」ことを心がけていきたいものですね。
男だから、夫だから上司だから父だから…そんな区分や役割にとらわれず、自分が心地よいと思うペースで生きていけるように、無理せず、ラクに、折れない心を育てていきましょう。では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分もSpotifyにて配信しています。 -
きっとだいじょうぶ スキーキャンプに参加しています
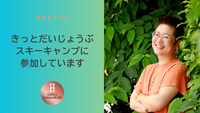
いつもご覧いただきありがとうございます!
昨日から、長野県に来ています。3年連続です。
今年は長男が行かないというので、次男とふたりです。
長男がひとりで留守番できるのはこちらの準備があってのこと 途中の羅臼庵で食べるお蕎麦が楽しみ。何をしに来ているかというと、もちろんスキー!なのは子どもだけで、私はケガの心配もあり専らおしゃべりを楽しんでいます。障害を気にせず、人の目も気にせず、似たようなからだのオトナや子どもとわいわい過ごす3日間は、めちゃリラックスできます。小さい子が私の手をじぃっと見てても、ぜーんぜん腹立たない。なぜならその子も私みたいな手だから。
途中の羅臼庵で食べるお蕎麦が楽しみ。何をしに来ているかというと、もちろんスキー!なのは子どもだけで、私はケガの心配もあり専らおしゃべりを楽しんでいます。障害を気にせず、人の目も気にせず、似たようなからだのオトナや子どもとわいわい過ごす3日間は、めちゃリラックスできます。小さい子が私の手をじぃっと見てても、ぜーんぜん腹立たない。なぜならその子も私みたいな手だから。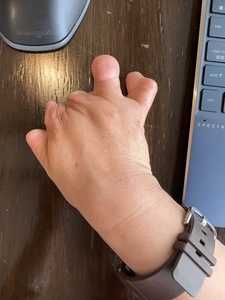 私の右手です。左手も個性的よ(笑)。知らんヤツがジロジロ見てきたら、普段ならイラっとするんですけど。これからまだまだ人生に大変なことが待っているであろう、後輩ちゃんたちですからねー。優しい気持ちで接することができます。ちょっとゆっくり話せるときは、これまでの知識と経験をイヤというほどお伝えできます(笑)。
私の右手です。左手も個性的よ(笑)。知らんヤツがジロジロ見てきたら、普段ならイラっとするんですけど。これからまだまだ人生に大変なことが待っているであろう、後輩ちゃんたちですからねー。優しい気持ちで接することができます。ちょっとゆっくり話せるときは、これまでの知識と経験をイヤというほどお伝えできます(笑)。
私たちくらい、過ぎ去ってしまえば何でもネタとして笑って話せますが、思春期の子たちの心労はいかばかりか。20年後もたぶん元気に暮らしていると思うよ、っていう、ちょっとだけ遠い視点を持って生活してくれたらいいなー、って思っています。 こちらは、あるご家族のスキーグッズの収納運搬方法。とりあえず何でも吊ってあるらしいです。使っているのは100均のプラチェーンとS字フック。クローゼットに吊るして、乾かして保管、まるっと持って来たそうで。今回参加してない人の分もそのままあるという、なんとも豪快な方法でした。
こちらは、あるご家族のスキーグッズの収納運搬方法。とりあえず何でも吊ってあるらしいです。使っているのは100均のプラチェーンとS字フック。クローゼットに吊るして、乾かして保管、まるっと持って来たそうで。今回参加してない人の分もそのままあるという、なんとも豪快な方法でした。
片づけのプロとしても勉強させていただいており、また各種ご相談にも対応させていただいておりまして、ただ遊んでリラックスしているだけじゃござんせんよ。父母の会では活動を支えてくださる賛助会員さんを募集しております。何らかの身体障害をお持ちの方のご入会も大歓迎です。上のリンクからお問い合わせくださいね。
私に聞いてくださってもOKです。
どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
男性が「助けを求める」のが苦手な理由~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ④
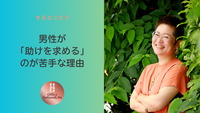
いつもご覧いただきありがとうございます!
今日のテーマは【チーム家族】【チーム職場】(笑)です。
「1人でなんとかする」は限界がある!
サポートを受けるのは恥じゃない
現代の男性は、仕事でも家庭でも
「自分が頑張らないといけない」
「1人でなんとかしないといけない」
と思い込んでいることが多いのではないでしょうか。
しかし、その考え方は時に大きな負担となり、心身の疲弊につながることもあります。
実は、「助けを求める力」こそがレジリエンス(回復力)を高める重要な要素なのです。
人生はチーム戦。
家族、職場の仲間、友人といった「チーム」の力を活用することで、より柔軟に困難を乗り越えられるようになります。
男性が「助けを求める」のが苦手な理由
多くの男性が助けを求めるのをためらう背景には、社会的な価値観や固定観念が影響しています。
「男は強くあるべき」という文化日本では昔から「男性は家族を支える存在」「弱音を吐いてはいけない」という考え方が根強くあります。
このプレッシャーが「人に頼るのは恥ずかしい」という思いにつながっています。
「迷惑をかけたくない」という気持ち
「自分の問題は自分で解決するべき」「他人に頼るのは甘えだ」と考える人も多いです。
しかし、実際には助けを求めることで、関係性が深まることもあります。
過去の経験や成功体験
これまで1人で乗り越えてきた成功体験があると、「今回も自分でなんとかできるはず」と思ってしまいがちです。
しかし、環境が変化する中で、1人の力だけで対応し続けるのは難しくなります。
「助けを求める力」もレジリエンスの一部
レジリエンスとは、困難やストレスを乗り越える力のことを指します。
昨日も書きました「本当の強さとは? 男性のレジリエンスについて考える」が、【強さ】とは、一般的には「折れないこと・精神的にタフであること」と思われがちですが、実際には「適切にサポートを求め、周囲と協力するしなやかさ」も重要な要素です。
助けを求めることで得られるメリット
助けを求めることで得られるメリットは数多くあります。
- 精神的な安定
1人で抱え込まずに話すことで、気持ちが軽くなります。 - 新しい視点が得られる
他人の意見を聞くことで、自分では思いつかなかった解決策が見つかることもあります。 - 問題解決のスピードが上がる
自分だけで悩むよりも、周囲の知識や経験を活用することで、より早く解決に向かえます。
助けを求めるための具体的なアプローチ
「助けを求める」と言っても、具体的にどうすればいいのか分からないという方もいるかもしれません。
その場合は、以下のような方法を試してみてください。
- 小さなことから頼んでみる
いきなり大きなお願いをするのはハードルが高いので、「ちょっとしたこと」を頼むことから始めましょう。 - 具体的に伝える
「ちょっと手伝ってほしい」ではなく、「◯◯をしてくれると助かる」というように具体的にお願いすると、相手も動きやすくなります。 - 感謝の気持ちを伝える
助けてもらったら、「ありがとう」としっかり伝えることで、相手との関係が良好になります。
ライフオーガナイズの視点:チーム家族の考え方
ライフオーガナイズでは、
「すべてを1人でやるのではなく、仕組みをつくってみんなでシェアすること」を大切にしています。
片づけも家事も、家族みんなで役割を分担すれば負担が減り、より快適な暮らしが実現できます。家庭でも職場でも、「自分が全部やらなければ」と思わず、「チーム家族」「チーム職場」として協力する姿勢を持つことが重要です。
特に、自分は稼いでいるから家事免除、でもありません。独身であれば、たとえ働いていても、当然生きていれば住居を汚します。家事から逃れられるものではありませんよね。家族がいても、自分ごととして家事をこなすのは当然のことです。家族とは家事、職場では同僚・上司と役割分担を明確にし、困ったときは遠慮せずに相談しましょう。
先延ばしするともっと大変になりますよね?早めの相談がキモです。ぜひ、幸せで充実した暮らしを叶えていただきたいです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分もSpotifyにて配信しています。 - 精神的な安定
-
本当の強さとは? 男性のレジリエンスについて考える
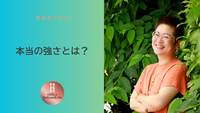
いつもご覧いただきありがとうございます!
「しなやかな生き方」— 強さとは折れないこと
生きづらい男性が、どうしてもっと生きやすさを追求しないのか?最近ずっと考えていることです。男性の生き方として、メタセコイアのようにどっしりと根を張り、太く、長く、力強く生きること。
これを理想として、多くの人が思い描いているかもしれません。
しかし、実際のところ、真に生きやすいのは、竹や柳のように「しなやかで折れない生き方」ではないか?
今回は「本当の強さとは?」について、考えてみたいと思います。
強さとは「耐えること」ではなく「しなやかであること」
私たちは時に、「強くあらねばならない」と思い込みます。
困難に直面した時、歯を食いしばり、耐え忍ぶことが美徳とされがちです。
でも、頑丈なものほど、一度の衝撃でバキッと折れてしまうことがあります。
一方、竹や柳は、風が吹けばしなやかに揺れ、雪が積もればしなだれる。
力をうまく受け流し、簡単に折れることはありません。
強いというのは「壊れない」ことではなく、「適応できる」こと。
これが、本当にラクに生きるための秘訣ではないでしょうか?
しなやかな生き方が求められる時代
現代は、変化の激しい時代です。
仕事のスタイル、人間関係、ライフステージ――どれも予測不能なスピードで変わっていきます。
そんな中、「こうあるべき」「こうでなければならない」とガチガチに決めつけると、柔軟に対応できず、ストレスが溜まってしまいます。
逆に「まぁ、なんとかなるか」「これも一つの流れかもしれない」と受け流すことができると、心の負担はぐっと減ります。
「揺れること=ブレること」ではありません。
むしろ、しなやかに揺れながらも、しっかり根を張り自分の軸を持っていれば、折れることなく生きていけます。
折れない心を育むために
では、どうすれば竹や柳のような生き方ができるのでしょうか?
ポイントは「執着を手放す」ことにあります。
100%完璧を求めない
すべてを完璧にこなそうとすると、失敗や変化に弱くなる
「まぁ、6~70%できていればOK!」くらいの気持ちでいることが大切
「こうあるべき」思考を減らす
「こうすべき」「こうでなければならない」という思い込みが、自分を苦しめる
柔軟に選択肢を持つことで、気持ちの余裕が生まれる
周囲と比較しない
人と比べることで、「自分はダメだ」と思う必要はない
自分のペースで、自分のやりたいことを大切にする
環境を整える(ライフオーガナイズの視点)
「思考の整理」ができると、自然とストレスが減る
モノや情報の取捨選択をすることで、心のスペースが生まれる
しなやかに生きるために、自分のペースを大切に
強くあることは大事です。
でも、それは「無理をして耐える」のではなく、「柔軟に変化できる」力があるということ。
竹や柳のように、しなやかでいながら、自分の根をしっかり張ることができれば、どんな風が吹いても、どんな雪が降っても、大丈夫。
自分の根をしっかり張るということは、価値観を明確にすることです。
しなやかな生き方を実践するためには、自分の思考や感情を整理することが大切。
ライフオーガナイズの考え方を取り入れながら、自分らしい「しなやかな生き方」を見つけていきませんか?
男だから、夫だから上司だから父だから…
そんな区分や役割にとらわれず、自分が心地よいと思うペースで生きていけるように、無理せず、ラクに、折れない心を育てていきましょう。では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分もSpotifyにて配信しています。 -
家庭と趣味を両立するために、まずやるべき3つのこと~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ②

いつもご覧いただきありがとうございます!
男性が、仕事で家を空けがちなのに、在宅時や休日も自分を優先してばかりだったら、きっと家族の不興を買うことでしょう。
ツーリング・ドライブや、釣りや、ゴルフなど、趣味を持つ方は少なくありません。そこで!
円満な家族運営のために、レーシングチームのようなマネジメント要素を入れて取り組んでみるのはどうでしょうか?まぁちょっと、話だけでも聞いてみてくださいよ(笑)。家庭と趣味を両立するためのオーガナイズ戦略
例えばこんなのはどうでしょう?
チーム戦のマインドを持つ
行動プラン
- 家族ミーティングを定期開催(レースの計画だけでなく、家族イベントも共有)
- パートナーの【得意】を活かす(例えば、料理が得意なら片づけは自分が担当する)
- お互いの優先順位を把握する(家族の大事なイベントはスケジュールに組み込む)
- 趣味に家族を巻き込む(一緒にレース観戦する、サーキットに遊びに行く機会を作る)
チェックリスト
- 週1回、家族とスケジュールをすり合わせたか?
- 自分の趣味ばかり優先してないか、パートナーの希望も考えたか?
- 家族の趣味や好きなことにも関心を持ったか?
メンテナンスタイムを確保する
行動プラン
- 家族サービスもスケジュールに組み込む(例えば、「日曜午前は家族デー」など)
- 効率的な家事ルーチンを作る(朝の15分で片づけ、夜の5分で次の日の準備)
- 【やらないこと】を決める(例えば、完璧な掃除よりも、片づけやすい仕組みを優先)
チェックリスト
- 家族と過ごす時間を「先に」確保したか?
- 家事を分担or効率化できる方法を考えたか?
- 【やらなくていいこと】を減らせているか?
ピットストップ戦略を立てる
行動プラン
- 家の中の動線をレース仕様に最適化!
- ワンタッチで片づけられる収納(フック・ボックス活用)
- 使ったらすぐ戻せる配置(利き脳※を意識した収納)※詳しくはお尋ねください。
- 時間がない時でも片づけられる導線(例えば玄関に荷物置き場を設置)
- 3分片づけルールを導入
- 出発前の3分で玄関を整える
- 帰宅後の3分でレーシングギアを整理する
- 風呂上がりの3分で翌日の準備
- 家族とタスクセッション
1週間のタスクを分担し、無理のない範囲でお互い協力すると、すばやくピットアウトできますね!
チェックリスト
- 片づけのハードルを下げる収納の工夫をしたか?
- 「時間がなくてもできる家事の仕組み」を作ったか?
- 家族と家のタスクをシェアできているか?
レースと家庭、両方勝ちにいこう!
レースと同じで、 準備と戦略・メンテナンスが勝敗を分けます。
家族との時間も、仕組みづくりができれば 「お互いハッピーな勝ちパターン】が作れるかも!
ぜひ、自分ごととしてチーム戦略を立ててみてください。幸せな家庭運営のお役に立てるとうれしいです。では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分もSpotifyにて配信しています。 -
子育て夫婦のすれ違いを解消する ほんのおすすめ

いつもご覧いただきありがとうございます!
いくつになっても、幸せな二人でいるために。
子育て夫婦のすれ違いを解消する〜『愛を伝える5つの方法』で関係を深めよう〜
今日は一冊ご紹介。
「なんだか最近、夫婦の会話が減った」
「子どものことで精一杯で、パートナーとの関係が後回しになっている」——そんな風に感じることはありませんか?
子育て中の夫婦は、とにかくお互いに忙しく、どうしてもすれ違いが生じがちです。(そして今、私の脳内にはユニコーンが…流れています)
ふと気がつけば、相手のことを思いやる余裕がなくなり、
「ちゃんと伝えているはずなのに、なぜか伝わらない」と悩んでたりしませんか。
そこで今回は、ゲイリー・チャップマン著『愛を伝える5つの方法』(The Five Love Languages)をもとに、子育て中の夫婦がより良い関係を築くためのヒントをご紹介します。
『愛を伝える5つの方法』とは?
毎度お世話になっております、公認心理師の植木希恵さんが主催するお母さんのための心理学講座で、この本の存在を教えてもらいました。
愛の伝え方には5つの「言語」があるとされています。
人それぞれ愛情を感じるポイントが異なるため、自分の愛の言語とパートナーの愛の言語が違うと、気持ちが伝わりにくくなってしまいます。
巻末に、夫・妻それぞれ30問の確認テストがあります。
タイプを知って、内容を読むと、より活用できると思います。まずは、子育て中の夫婦が感じるすれ違いを解消するために、この本をどのように活用できるのか?ご紹介していきます。
5つの愛の言語と実践方法
1. 肯定的な言葉(言葉で愛を伝える)
子育てに追われる日々では、お互いにイライラしがち。
しかし、意識して「肯定的な言葉」を使うことで、相手への感謝や愛情がしっかり伝わるようになります。
- 「ありがとう」「助かるよ」と、相手の行動を認める言葉を意識する
- 「お疲れさま」など、労いの言葉をかける習慣をつける
- 「ちゃんと伝わってるかな?」と考えながら、普段より少し多めに言葉をかける
2. クオリティ・タイム(一緒に過ごす時間)
子ども中心の生活になり、夫婦の時間が減ってしまうのはよくあること。でも、大切なのは「短い時間でも、お互いに意識を向けること」です。
- 子どもが寝た後、10分だけでも一緒にお茶を飲みながら話す
- 家事をしながらでも、目を見て会話する
- 忙しくても、週に1回は一緒に映画を観る、散歩するなどの時間を作る
3. 贈り物(プレゼントで気持ちを伝える)
「ちょっとした贈り物」には、相手のことを考えているという気持ちが込められます。
- 相手の好きなお菓子や飲み物を買っておく
- メモやLINEで感謝のメッセージを送る
- 手紙を書いて枕元に置いておく
4. サービス行為(行動で愛を示す)
言葉やプレゼントよりも、行動で愛を感じるタイプの人もいます。
- 仕事や家事で疲れているパートナーのために、ちょっとした家事を代わる
- 子どものお風呂や寝かしつけを引き受けて、相手のリラックスタイムを作る
- 「やってあげる」のではなく、「相手の負担を減らす」意識を持つ
5. 身体的なスキンシップ(触れ合いで安心感を与える)
忙しいと、スキンシップが減ってしまいがち。でも、触れ合うことでお互いの心の距離も近づきます。
- 朝や帰宅時に軽くハグをする
- 手をつなぐ、肩を叩くなど、小さなスキンシップを増やす
- スキンシップが苦手な相手には、無理のない範囲で自然に距離を縮める
夫婦関係を良くするためには、自分の「愛の言語」を知り、相手の言語も理解することが大切です。
親子でも言語が違えばめちゃ行き違いに…。
自分のタイプと親しい誰かのタイプ、知っていることでよりよいコミュニケーションができるはず。でも、いきなり大きく変えようとするのではなく、小さなことから始めてみてください。
「こんなことではどうせ伝わらない」と決めつけずに、少しずつ積み重ねていくことが大切。
夫婦の関係が良くなると、子どもにも安心感が生まれます。
子どもって、どんなに小さくてもよく感じ取っています。ぜひ、できることから試してみてくださいね!
というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
夫が自ら気づき変わると、もっと幸せになれる~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ①
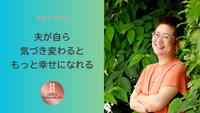
いつもご覧いただきありがとうございます!
ちょっと最近深く刺してる気はしてますが、夫が変わることで家族はめちゃめちゃ幸せになる!と思っておりますので、今日はなるべくソフトにお伝えできたらなと思います。とはいいつつ、いきなりですが、家のこと、どうしてますか?- 自分からやる
- 分担が決まっている
- 聞いてからやる
- 言われたらやる
- 言われたら渋々やる
- 言われても無視
- 言われたらキレる
- 言われたくないから家にいないようにしている
もし今からちょっとでも関係改善しようと思うなら、しばし己を振り返ってみてください。自己チェック
あなたは以下の点について、どうしていますか?どうとらえていますか?
家事・育児の分担
- 家の中で、自分がやっていることは何か?
- もし自分が1週間 家事を全部やるとしたら、何が一番大変だと思うか?
- 子どもが「パパがしてくれて嬉しい!」と言うのは、どんなことか?
- 気づきのポイント
「手伝う」ではなく「共にする」という意識にシフトすると、夫婦・親子関係が好転!
妻の気持ちやストレスに気づく
- 最近、妻が疲れてるな~って思ったことがあるか?
- 自分が仕事から帰ってきたとき、妻はどんな表情をしているか?
- 自分がもし妻の立場なら、何をしてもらえたらホッとするか?
- 気づきのポイント
妻の気持ちに敏感になることで、コミュニケーションが円滑になり、結果的に自分も居心地が良くなる!
お金の使い方や価値観のすり合わせ
- 自分と妻、お金の使い方で大事にしてるポイントはどこか?
- お金のことで、妻が不安に思ってることは何か?
- 夫婦でお金のことをちゃんと話したのは、直近でいつのことか?
- 気づきのポイント
お金の価値観をすり合わせると、将来への安心感が生まれ、夫婦の信頼が深まる!
感謝や愛情表現を増やす
- 最後に妻に「ありがとう」って言ったのは、いつだったか?
- 付き合ってた頃みたいにデートしてみたら、どんな気分になるだろうか?
- 妻が「私は大事にされてる」と感じるのは、どんな時なのか?
- 気づきのポイント
感謝や愛情は「伝えてるつもり」ではなく「きちんと相手に伝わっているか」が大事!
夫婦の将来について考える
- 5年後、10年後、夫婦としてどういう関係でありたいか?
- 老後はどんな暮らしをしたいのか?
- 今からできることは何か?
- 気づきのポイント
長期的な目線で考えると、目の前のケンカや不満より「どうしたら一緒に幸せになれるか」が見えてくる!
日頃から、ともに家事育児をやることで、普段の関係性が劇的に変わります。
やり初めは気持ち悪がられても、くじけずに先輩主婦の指導を受けて上手になっていけば、妻は確実にラクになるので、イライラした様子も減ってくるかもしれません。
最初の質問に、「1週間家事をやるとしたら?」と入れましたが、妻が緊急的に入院することだって、あり得ます。そんな時にも、「俺はできる!」と思えれば、妻にも「勝手に体調を崩した文句」ではなく「安心して療養するように」優しい言葉をかけて労われると思います。今日は、チーム家族として、幸せな毎日を過ごしていただくための、振り返りの質問をしました。夫の変化は最も即効性があります。がんばっていきましょう!!笑顔あふれる幸せな家族が一つでも増えますように。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。