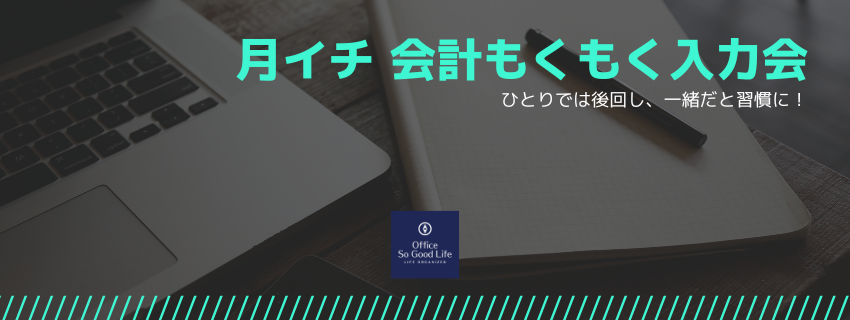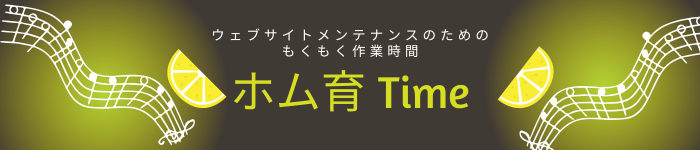- ホーム
- ブログ Drive my LIFE!
- ライフオーガナイズ
- 私の終活 改正原戸籍の取得
私の終活 改正原戸籍の取得
2023/02/21
いつもご覧いただきましてありがとうございます。
自分の死後、煩雑な手続きを、少しでもラクにしておくために出来ることをご提案。
戸籍請求手続き
今日のポイント
- なぜ必要?
- 誰が取る?
- いつ取る?
- どこでとる?
1戸籍が死後に必要な理由
人の死後には、故人だけでなく、家族親族分の戸籍が必要になるシーンがかなりあります。
生後(婚姻年齢からでも事足りるらしいですが)から現在までの戸籍謄本(改正原戸籍)を揃えます。
主に相続で必要となります。
- 遺言書の検認
- 相続税の申告・納税
- 生命保険金の請求
- 遺族年金の請求
・国民年金の遺族基礎年金請求
・国民年金の寡婦年金請求
・厚生年金の遺族厚生年金請求
- 名義変更
・不動産の名義変更
・預貯金の名義変更
・株式の名義変更
・自動車所有権の移転
・電話(加入固定電話)の名義変更
他にも、
太陽光パネルで売電されているおうちは売買契約書の名義変更もありますし、
敷地内に公共物(電柱など)がある場合も必要です。
2誰が取る?
人が死んでからだと、遺族が取りに行くことになりますが、本人以外による戸籍謄本請求手続きは、本人がやるよりも大変です。
故人との関係性の証明のため、持参する証明書の追加など手間が増えてしまいます。
交付申請できる人
- 本人及び現在同一戸籍の人
- 必要な戸籍に記載されている人の配偶者
- 必要な戸籍に記載されている人の直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)
- 正当な理由があって戸籍謄本等を交付申請する人(代理人が申請する場合は、委任状が必要)
3いつ取る?
上記の理由から、現在までの戸籍は、生きているうちから手元に揃えておくのがおすすめです。
故人の戸籍謄本が取れるタイミング
死亡届(死亡後7日以内に提出)を役所に提出
↓
届出の内容に問題がなければ、1~2週間後に「死亡」を戸籍謄本に反映
4どこで取る?
- 市区町村の役所
戸籍は、本籍地のある市区町村の役所で交付申請をします。
ですから、まず必要な戸籍の本籍地や筆頭者がわからないと請求できません。
親や家族に聞いても本籍地がわからない、という時は、先に本籍地・筆頭者の記載された住民票の写しを取得するといいですね。
窓口で必要書類と共に、「一生分の戸籍謄本を揃えたい」と伝えます。
そこで全部揃わないときは、次の戸籍がどこにあるかを聞いてみるといいでしょう。- 郵便による交付申請
戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法は、各自治体のホームページで詳しく説明しています。
戸籍に関する証明書交付申請書もダウンロードできるので、故人の本籍が遠方の場合は、利用してみましょう。- マルチコピー機
現在は(対応している市町村に限りますが)コンビニで本人がマイナンバーカードを使って請求できるようになっています。
おまけ
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
- 戸籍謄本と戸籍全部事項証明書は同じもの
戸籍謄本とは、戸籍の原本を全てコピーして、市区町村長名と公印等を押して証明した書類のことです。
「謄(とう)」とは、「全文写し」の意味で、戸籍に入っている人全員の情報が記載されています。
夫婦と未婚の子が2人いれば4人の、未婚の子のうちひとりが結婚すればその子は除籍され、3人の戸籍謄本になります。
現在では、戸籍の情報をコンピュータ化して保管するようになり、名称が戸籍謄本から戸籍全部事項証明書に変わっています。
- 戸籍謄本と戸籍抄本は違う
戸籍抄本とは、戸籍に記載されている人のうち、ひとり、もしくは複数人の身分事項を証明するものです。
「抄(しょう)」とは、「必要部分写し」の意味で、戸籍謄本と戸籍抄本で証明される身分事項について違いはありません。
こちらも電子化で呼称が個人事項証明書に変わりました。
既婚者はみなさんご経験でしょうが、結婚すると、夫婦ともに両親の戸籍から除籍され、新たな戸籍を作る仕組みになっています。
私はその後離婚したので、夫婦の籍から除籍しています。ですからそこには元夫がボッチです。
新たに私が戸籍を持ち、後に子どもたちを入籍し、私の旧姓への改姓を裁判所に届け出て変更した、という経過です。
これはね、あまり経験されていないかと思いますので今後のご参考までに。(え?何の参考?(笑)マジで名前の手続きってめんどくさいので夫婦別姓早く許可してほしいですよ。)
先延ばしにはできない話
私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。
-
 私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?
いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折
私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?
いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折
-
 私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅
いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ
私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅
いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ
-
 私、終活講座もやるんです 講師紹介
いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹
私、終活講座もやるんです 講師紹介
いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹
-
 レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる
いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾
レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる
いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾
-
 レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは
レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは
-
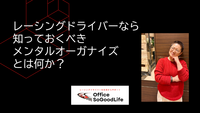 レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル
レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル
-
 レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!
いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備
レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!
いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備
-
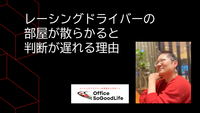 レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由
いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ
レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由
いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ