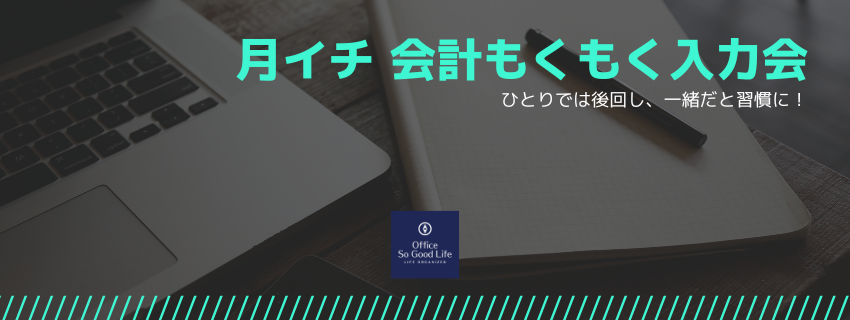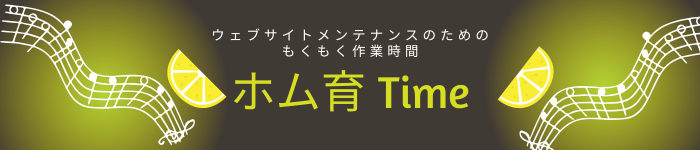- ホーム
- ブログ Drive my LIFE!
- 子育て
- 子どもが片づけません! それって誰が困ってますか?
子どもが片づけません! それって誰が困ってますか?
2023/02/25
いつもご覧いただきありがとうございます!
自分が多少散らかすのはいいけど、家族が片づけないのは腹立つ(理不尽w)。
でもそんなことないですか?
子どもに片づけさせたい!
- 自分は片づけられるけど、子どもは全然できない・やらない
- 自分が片づけられなくて困ったから、子どもにはできるようになってもらいたい
だから、子どもに片づけさせたい。
よく聞くお話です。
しかし。
誰かに何かをさせるのって、非常に難しいことじゃないですか?
自分の思考や行動を変えることも、まぁまぁ難しいです。
僻みっぽいとか
妬みっぽいとか
悲観しがちとか。
あと、やらなきゃと思ってても取り掛かれないことが、まぁまぁありますよね?
なんか無駄にダラダラしちゃう、とか。
やめたいと思ってもなかなか変えるのが難しいことって、たくさんあると思います。
オトナがそうなんですよ。
子どもって、どんなですかね?
短期記憶アヤシイ
子どもの記憶力・注意力って、どうですか?
朝起きてから学校行くまでのタスクを、抜けや漏れなくスムースに実行する機能が備わっているでしょうか?
うちの小学生たちは、毎日何かしら抜けてしまい、無駄な往復や二度手間三度手間が頻発しております。
うちだけ?と不安になったこともありますが、どうやらよそのお宅でも似たようなものみたいです。
5分10分の記憶もアヤシイのに、日々の行動をコントロールするのは、子どもにとっては至難の業なのかも知れません。
片づけが習慣にならない理由
【遊んだら片づける】
こんな簡単なことができないなんて、信じられない!
【ゴミはゴミ箱に】
どうしてほうりっぱなしにしちゃうの?
あるあるですよねー。
うちでも、
【席を立ったら後ろを振り返れ!】
と毎度言っております。
振り返りさえすれば、自分のいた場所がいかにひどい状態かがわかるというのに、全く振り向かないんです。
前しか見てない。視野もめっちゃ狭い。
うっかり「お見事!」と言いそうになります。
子どもは前しか見ていない
子どもが振り返らないのはごく単純につまらないからでしょうね。
終わったことは終わったこと。そこに興味はもうない。
「次何しよう!?」というワクワクがあるのは前だけ。
次の瞬間にもう気持ちが行ってしまっているので、片づけることなく、どんどんどんどんおもちゃを出していく。
なんならミックスして独自の遊びを展開していきます。
そして…
片づけの必要性を全く感じていないのに遊びの時間が終わったということで、大人から「片づけなさい!」と言われて初めて
「ガーーーーン‼‼」
「こんなにたくさんおかたづけできないよー( ノД`)シクシク…」
というのを、ほんとに毎度新鮮な気持ちでやってはるのが子どもというものです。
そんな人に、「片づけなさい」と言ったところで、ひとりでできるはずもありません。
そういう状態に、一番困っているのは誰でしょうか?
子どもでしょうか?
オトナでしょうか?
・・・
子どもはおもちゃに囲まれて幸せです。困ってはいません。
ということはそう、散らかされて困っているのはオトナですよね?
オトナが困っているのに、その問題解決のために子どもを動かそうとするのは、どうしても無理があります。
オトナの側の
『自分が使ったものは自分で仕舞うということを教えたい』という教育の側面と、
散らかっていると困る、
ということは、一旦分けて考えてみてはどうでしょうか。
教育は結果的にできたらええやん、っていうことにして、とりあえずは、子どもが「さぁ片づけよう!」と自ら行動するにはどう声を掛けたらいいか?について考えたいと思います。
片づけはつまらない、を変える
子どもにとっては、遊びに満足した後(あるいは強制終了だったりで)やりたくもない、やる意味も分からない片づけって、めっちゃイヤなことでしかないと思うんです。
しかも細かく分ける収納方法だと、子どもには難しすぎたりするので、ざっくり分け程度がよいかと思いますよ。
そして、片づけにゲーム性を持たせるのがよいのでは?と思います。
- トミカだけ選手権
- おえかき選抜
- オトナと競争
- タイムアタック
また、
- ラス1は誰だ!
一緒に片づけながら、最後のひとつは子どもに仕舞ってもらう、
などというように、遊びの延長で片づけることを繰り返し繰り返し、習慣づくまでやっていきます。
片づけの意味を伝える
そして片づけ終わったら、
「すごい!お部屋が広くなったね!」
「ゴロゴロ転がれるね」
「おもちゃがおうちに帰れて、ゆっくり寝られるね」
「スッキリするね」
「気持ちいいね」
などと声を掛けます。
「片づいていれば、次に遊ぶときにも、何がどこにあるかがすぐわかるよ!」
と、片づけの意味や効果について繰り返し伝えることが大切です。
なぜって?
子どもはすぐに忘れるから!です。
片づけって、小さい時からできるに越したことはないですが、できないからってすぐに死ぬようなことではありません。
だから、急いでやらせることはないと思います。キライになったら元も子もないですからね。
やり方が合ってる、合ってない、っていうことも多々あります。
押し付けずに一緒に試行錯誤する、これが片づけにおいて誰でも通る道です。
やり方が合ってる、合ってない、っていうことも多々あります。
押し付けずに一緒に試行錯誤する、これが片づけにおいて誰でも通る道です。
オトナが、子どもの成長に合わせた声掛けを学んで、ゆっくりでも着実にできることを増やしていけたらいいんじゃないかなと思っています。
片づけは、非常に高度な作業です。
焦らず、怒らず。
一緒に楽しみの要素を加えつつやっていきましょう。
お困りごとは、私がサポートいたしますので、お気軽に
無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。
私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
よかったら受講をご検討ください。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。
お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。関連エントリー
-
 私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?
いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折
私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?
いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折
-
 私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅
いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ
私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅
いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ
-
 私、終活講座もやるんです 講師紹介
いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹
私、終活講座もやるんです 講師紹介
いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹
-
 レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる
いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾
レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる
いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾
-
 レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは
レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは
-
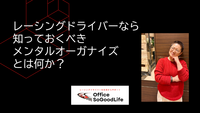 レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル
レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル
-
 レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!
いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備
レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!
いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備
-
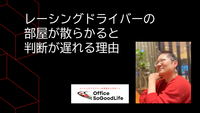 レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由
いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ
レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由
いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ