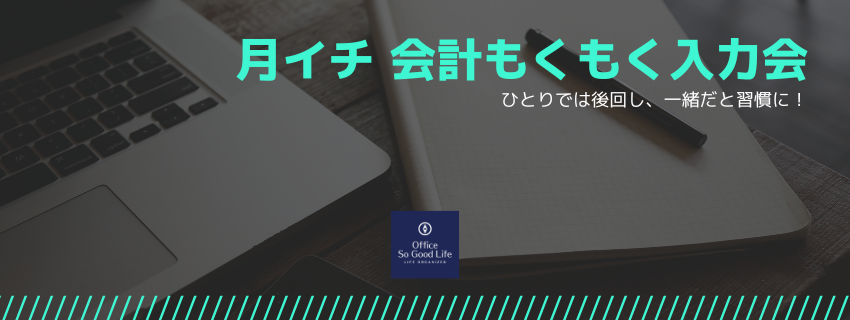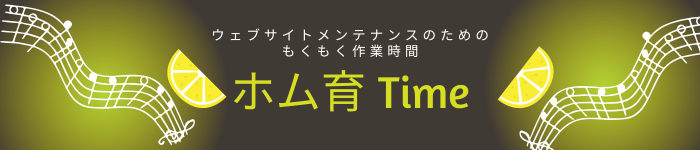- ホーム
- ブログ Drive my LIFE!
- ライフオーガナイズ
- 子どもと片づけ~作品の管理、どうしてる?
子どもと片づけ~作品の管理、どうしてる?
2023/04/04
いつもご覧いただきありがとうございます!
あっという間に春休みも終わりますね。
みなさん今頃は、新学期を前に子どもの持ち物を整理したり、新たに文具を買い揃えたりしていますよね。
もう準備万端!という方もいらっしゃるでしょうか。
さて(今頃ですが)修了式の日に持ち帰った作品はどうしていますか?
どんどん増える作品たち
わが家にも二人の息子たちの、保育所時代からの作品があります。
絵や制作、誕生日のカードや色紙、先生との連絡帳などもあります。
基本的には、平面の物は残していて、まとめて私が管理しています。
台紙に貼られた四つ切画用紙も余裕で入るこちら、
IKEAのSTUK (ストゥーク)収納ケース ライトグレーグリーン 71x51x18 cm
この中に仕舞っています。
長男が3歳から、次男が1歳からの作品をこの中に収めています。かれこれ8年分ですね。
季節の装飾として制作したもので、まだ耐用できるものは、もういいと思えるまで毎年時期に飾っています。
そういう立体のもの、季節ものは、別の装飾用BOXにまとめています。
私は主に玄関に飾るために残しています。
保育所で作った紙皿のおひなさまとか、自分の人形を年間のアイテムで彩っていくものとか、七夕のモビールとか、クリスマスの折り紙リースとか。
かわいくて愛おしくて、私が取っておきたいものがあります。
残したいものは残していい
『増え続ける作品をどうしよう?』と悩まれる方は多いです。
スペースに余裕があれば、いくらでも好きなだけ残して飾っておけますが、そうでない場合は工夫する必要があります。
- 子どもが多い
- 量が多い
- 子どもが多くて管理が大変という場合
ひとりずつの容量をあらかじめ決めておいて、いっぱいになったら中身を見直して、手放すものは写真に撮って保存することができます。 - 量が多くて管理が大変という場合
1の多子の場合と同じように、保管スペースからあふれるものは、
- 全部出して
- 残したいものを選び
- 他は撮影して手放す
これを毎年繰り返すことで、定量を維持することができます。
どれを残すか?を決めるのは、あなたひとりでもいいし、お子さん本人に意見を聞いてもいいですよね。
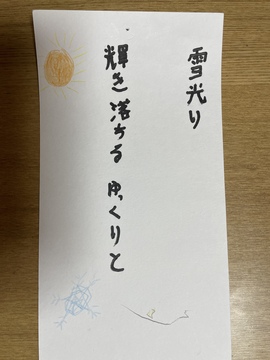
これは次男の作品です。
年度末に持ち帰ったものの中にあったんですが、これ、懇談に行ったときに見つけて、次男の感受性にびっくりしてうれしくなったのを思い出しました。
「光って輝くのか~、そうなのか~」と思いました。
というわけで、小さいものですがしばらくは保管です。
というわけで、小さいものですがしばらくは保管です。
どこに置くか
管理する場所が親のスペースである場合と、子どものスペースである場合があります。
おうちの状況によって違うと思いますが、どちらの場合でも、中身についてはスペースの管理者が把握しているべきです。
子どものスペースに置くということは、処分権が子どもに移るということ。
親のエゴで残したい作品であれば、親が管理する方がトラブルなく済みます。
親のエゴで残したい作品であれば、親が管理する方がトラブルなく済みます。
親のところにはスペースがなくて仕方なく子ども部屋に、という場合は、きちんと本人に了承を得て、置かせてもらいましょう。
こういうけじめが大切です。
時期を決めて中身を見直す
学期ごとに作品を持ち帰るのであればその都度、年度末だけであれば、1年に1度ですが、必ず中身を見直しましょう。
成長とともに、あるいは時間の経過とともに、「もういいかな」と思えて手放せるものが出てきます。
そういうものは忘れてしまってもいいし、写真で思い返してもいいんです。
教科書なども同様です。
単年度の物は、全部捨てても問題なし。
資料集などは置いてあった方がいいこともありますが、ほとんどは使いません。
残したかったら残していいし、要らなかったら捨ててもいい。
収納スペースに対し80%の物量に留めておくことが、出しやすく戻しやすい収納の基本です。
総量を決めて、いちいち考えない仕組み
- 必要なものを選ぶ
- 入る分だけ残す
- 思いが残っているものは捨てない
このルールを守ることで、かなりラクに過ごせるようになりますよ。
お子さんの片づけにも適用できます。
- うちの場合、どうすれば?
- 子どもと決めるのは難しそう…
ひとりではちょっと、という場合は、遠慮なくご連絡ください。
プロを頼るのは恥ずかしいことでも何でもありません。
快適な生活への近道をご案内いたしますので、お気軽に
ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談をご活用くださいね。
私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月19日より開講。お申込みはお早めに!
関連エントリー
-
 私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?
いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折
私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?
いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折
-
 私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅
いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ
私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅
いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ
-
 私、終活講座もやるんです 講師紹介
いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹
私、終活講座もやるんです 講師紹介
いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹
-
 レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる
いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾
レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる
いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾
-
 レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは
レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは
-
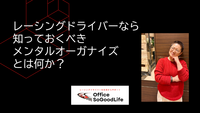 レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル
レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル
-
 レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!
いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備
レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!
いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備
-
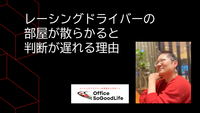 レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由
いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ
レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由
いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ