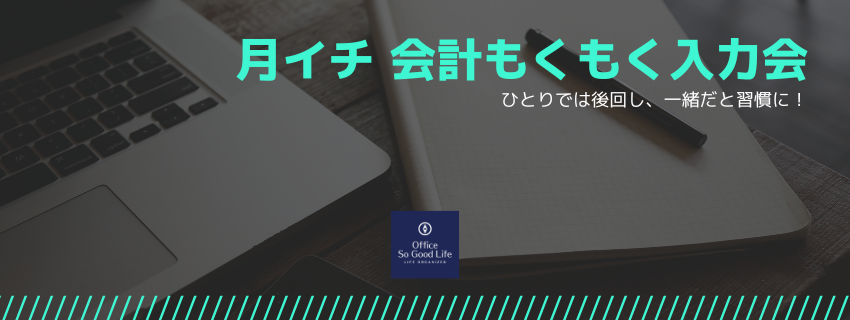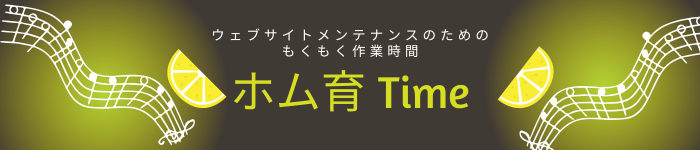- ホーム
- ブログ Drive my LIFE!
- ライフオーガナイズ
- 防災 あなたの避難場所を知っていますか?
防災 あなたの避難場所を知っていますか?
2023/02/14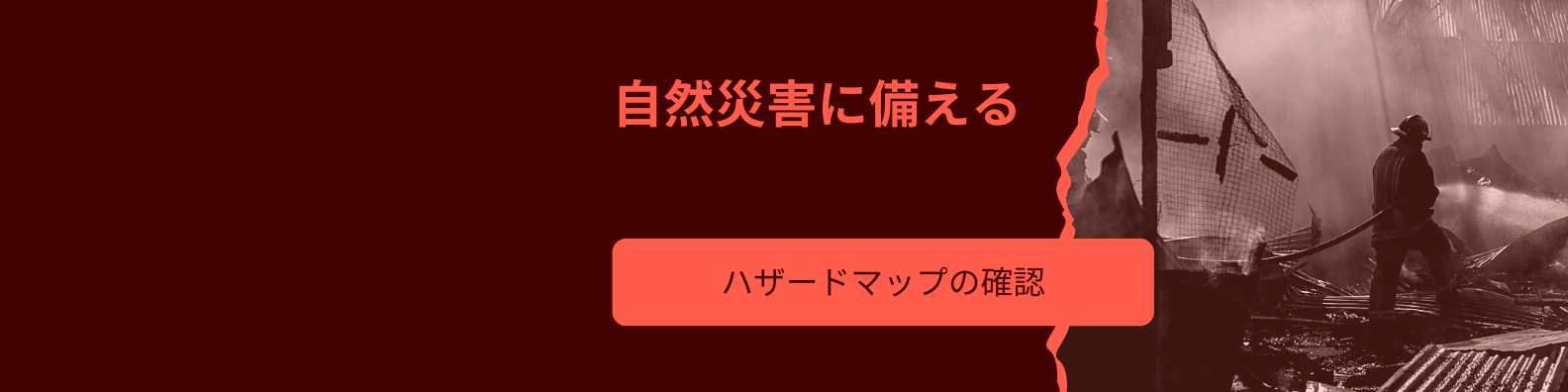
いつもご覧いただきありがとうございます!
本日は何かあった時のために。
確認しておきましょう!
あなたのお手元に、地域の【ハザードマップ】【防災マップ】はありますか?
不明な方。
捜しましょう。
捜して見つからなければ、市役所や公民館でもらってきてください。
とても大事なものです。
いつでもさっと確認できるところに保管しましょう。くれぐれもよろしくお願いします。
家族防災会議のススメ
【ハザードマップ】【防災マップ】には、避難場所が書かれているだけでなく、浸水予想エリアや、土砂災害警戒区域なども明示されています。
それらとお住まいの位置関係がどうなっているか?を知らないと、どっちに逃げたらいいかわかりませんよね。
ですから、お子さんも含めて、家族みんなで一緒に地図を確認してみましょう。
なにも家族が一緒にいる時に被災するとは限りません。
夜、みんなで家にいる時に限って起きる、と決まっているわけではなく、日中バラバラで活動している時に発生するかもしれません。
子どももそれぞれ、今いる場所から自分がどこに逃げたらいいのかを知らないと、命を落とします。
ですから、それぞれ普段の活動範囲を基本に、いつ、どこからでも適切な場所に逃げられるように備えておきましょう。
学校でも、学年に応じてある程度の防災授業があり、教育をされています。
もしかしたら、お子さんの方がいろいろと知っているかもしれませんね。
どこに逃げる?
- 避難所
さて、防災マップに記載されている避難所ですが、実は災害の種類によって開設される避難所が違います。
さっきみんなで確認した危険エリアはどうなっていますか?
地震・津波と、台風など大雨被害では、逃げる場所が違いますよね。
ですから開設避難所が違うんです。
また、開設順序もあります。
いつでも小学校や中学校が避難所になるわけではないので、各自治体での取り決めを確認してください。
地区の避難所が開設されたら通知が来るように、自治体のメールを受信できるよう設定しておきましょう。
- 自宅
いつも避難所に行くのが最善とは限りません。
しかし時と場合によるのでこれが正解、ということもできません。
前提条件として、身を守るための出来る限りの手を打っての後ですよ、
- 報道以上の大雨で、付近が既に浸水してしまい、避難所まで移動する方が危険な場合や、
- 夜間の避難なんかは、訓練なしには不可能です。
災害の種類によっては自宅で救助や復旧を待つ方がよい場合もあります。
最近はむしろこちらの方が勧められるシーンも増えてきました。
外に逃げられない時は2階に上がって!という垂直避難もありますね。
ですから、2階でもしばらく過ごせるように、トイレや食糧など備蓄品の扱いを考えないといけません。
キッチンの近くと2階とに分散させるのか?さっと運ぶのか?
状況によって、その都度いちいち考えずにパッと動けるように、予め決めておくことが大切です。
地震はいつも突然ですし、規模も分かりませんからまさに出たとこ勝負ですね。
どの場合にどこでどう過ごすのか?
是非シミュレーションをしてみましょう。
災害対策公園
【災害対策公園】って、聞いたことありますか?
広めの公園で、
水がなくても使えるようにマンホールの上にすぐ設置できる簡易トイレ用のスペースがあったり、
ベンチがかまどになったり、
東屋がすぐテントになって、避難者対応の窓口を設置できるようになっていたりします。
お住まいの地域にあるかどうか、確認してみてください。
どういう時に利用できるのか?も併せて確認が必要です。
キャンプ道具をお持ちの方は、いつでも使えるように、整備しておいてくださいね。
レジャーだけで終わらせてはもったいないです。
困ったらぜひ相談を!
私のおすすめは、同じ中部エリアで活動する、こゆきちゃん、こといのうえゆきさんです。
地域で防災ボランティア活動もしています。彼女の備蓄の持ち方についてのアドバイスは、すごく論理的でわかりやすいです。
私は、地域のファミリーサポートセンターに提供会員として登録しており、よそのお子さんを預かる機会があることから、災害時の対応・避難についても毎年教育を受けています。
こういう時どうするの?といったご相談にものれますので、お気軽に
無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。
私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。
お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。関連エントリー
-
 私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?
いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折
私、終活講座もやるんです⑤学んでも、一人では進まない?
いつもご覧いただきありがとうございます!定休日は、現在募集中の講座をご紹介しています。挫折
-
 私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅
いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ
私、終活講座もやるんです⑥現代必須の項目を網羅
いつもご覧いただきありがとうございます!今回内容紹介するのは、とても見えにくいもの!デジタ
-
 私、終活講座もやるんです 講師紹介
いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹
私、終活講座もやるんです 講師紹介
いつもご覧いただきありがとうございます!よりよく生きる終活講座 season6 の講師を紹
-
 レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる
いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾
レーシングドライバーは挨拶ができるだけで 評価は大きく変わる
いつもご覧いただきありがとうございます!挨拶で評価がここまで変わる最近は、挨拶を軽んじる傾
-
 レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは
レーシングドライバーの感情は 否定せずに片づければ武器になる
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマは感情の取り扱い方。感情的になることは
-
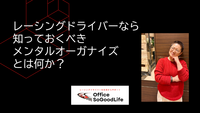 レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル
レーシングドライバーなら知っておくべき メンタルオーガナイズとは何か?
いつもご覧いただきありがとうございます!今日のテーマはメンタルオーガナイズって何?メンタル
-
 レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!
いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備
レーシングドライバーの日常は【パッケージ化】で思考サクサク!
いつもご覧いただきありがとうございます!出張・サーキット走行・シミュレーターレースは、準備
-
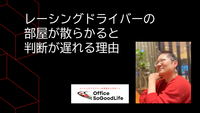 レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由
いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ
レーシングドライバーの部屋が散らかると判断が遅れる理由
いつもご覧いただきありがとうございます!ここから、片づけについてお伝えしていきます。ライフ